
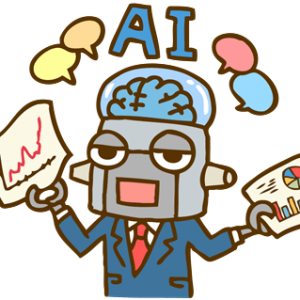 なるほど君
なるほど君 この記事を読めば分かること
- 牡蠣を食べてはいけない時期
- 夏と冬、どちらが当たりやすいか?
- 生牡蠣を食べる際の注意点
牡蠣にあたる期間や時期には目安があるのでしょうか?
冬は当たりやすい、いや夏のほうが腐りやすいから当たりやすい、など様々な説があってはっきりしません。
どの季節があたる確率が高いのか、症状が出るまでの時間はどれくらいなのかなど、生ガキを食べるにあたって知っておきたいことをまとめてみました!
牡蠣を食べてはいけない時期

外国の映画や小説で、こんな説を目にしたことはありませんか?
つまり、月の名前を英語で書いたときに「R」が付かない月に牡蠣を食べると「あたる確率が高くなる」というわけですね。
英語の月名一覧と「R」の付かない月は?
●1月 : January←OK
●2月 : February←OK
●3月 : March←OK
●4月 : April←OK
●5月 : May←「R」が付かないからダメ
●6月 : June←「R」が付かないからダメ
●7月 : July←「R」が付かないからダメ
●8月 : August←「R」が付かないからダメ
●9月 : September←OK
●10月 : October←OK
●11月 : November←OK
●12月 : December←OK
ちょうど5月から8月にかけての気温が高い時期が該当しますので、経験から導き出された「経験則」のように見えますね。
この言い伝えというかジンクスは、18世紀のフランスが発祥とされています。
当時は現在のように海で牡蠣を採っても内陸部のパリまで腐らせずに運搬することが難しかったとか。
そんな事情から「気温の高い時期=腐りやすい」ので、このような警告が実感を持って信じられていました。
ですから18世紀と比べて格段に冷蔵保存が発達した現代では、必ずしも守らなくてもいいみたいですよ。
ノロウィルスが多く発生する時期ともズレていますから。
生牡蠣は夏と冬、どの期間や時期があたる確率が高い?
牡蠣を生で食べた時に「あたる」のは夏と冬ではどちらの期間(時期)が確率が高いのでしょうか?
そもそも「牡蠣にあたる」とはノロウイルス(SRSV小型球形ウイルス)に感染することを意味します。
このノロウイルスが発生しやすいのは冬の11月~3月にかけて。
なので、当然ながら牡蠣に当たりやすいのは夏よりも冬のほうが確率が高いと言えます。
牡蠣に当たらないために最低限守らないといけないこと
スーパーの鮮魚売り場で並んでいる牡蠣のパックには「生食用」と「加熱処理用」があることにお気づきでしょうか?
生食用牡蠣と加熱調理用牡蠣の違いは?
●生食用・・・綺麗な海域で採れたもの/殺菌して出荷されたもの
●加熱調理用・・・一般の海域で採れたもの/殺菌処理されてないもの
つまり加熱調理用は、鍋やカキフライなど加熱調理して食べることを前提に販売されているというわけです。
なので間違って加熱調理用牡蠣を生食してしまうと「当たりやすい」わけですね。
これは
※生食用の牡蠣なら絶対に当たらないという保証はありません。
食中毒の症状が出るまでの時間はどれくらい?

生牡蠣を食べたその日は平気だったのに翌日になってから体調が悪くなった・・・・・なんてことありませんか?
実は食中毒の症状が出るまでの時間はこんなに幅があるんです。
食べてすぐに症状がでなくても1日経ってから、急に嘔吐や下痢といった典型的な食中毒症状がでる場合があります
この症状がでるまでの時間を「潜伏期間」と呼びます。
牡蠣の食中毒の症状一覧
- 嘔吐
- 下痢
- 吐き気
- 腹痛
- 発熱
しかし、24時間経たないと症状が出ないかというとそうでもなくて、なかには食べてから30分~1時間で「あたった!」と分かるほど急激な症状が見られる場合もあります。
【まとめ】「家でも食べたいなぁ~~~」
水揚げされたばかりの新鮮な牡蠣が食べられる魚市場や、おしゃれなオイスターバーでしか「当たらない」生牡蠣を食べられないものと思ってまし。
でも、家でもちゃんとした知識を持って選んで買えば食べられることが分かってうれしいです♪
牡蠣ってタウリンとビタミンB1や亜鉛など栄養豊富ですから、旬の冬じゃなくても食べたいですよね。