
立冬の食べ物って何か特別なものがあるのでしょうか?
単純なイメージでカボチャが思い浮かびますが、それって本当なのでしょうか?
そこでこの記事では
- 立冬の食べ物でかぼちゃは間違い?
- 立冬の食べ物は何を用意する?
- 日本と中国の違い
- 2025年の立冬の日付
- 立冬の意味や由来
など、ひとまとめにしてご紹介します。
立冬の食べ物はカボチャ?

一年の暦上の節目の日には特別な食べ物を食べるのが普通です。
では立冬はどうなのかというと、特別に食べるものは昔からありません。
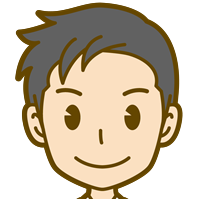
あれ?立冬はかぼちゃじゃないの?
と疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、かぼちゃを食べるのは冬至のほうです。
名前が似ているので混同している方が多いようですね。
ちなみに立冬の由緒正しい歴史ある食べ物とは言えませんが、現代になってこんな2つの食べ物を食べる日に認定されています。
あられ・おせんべいの日
全国米菓工業組合が1985年に制定した日。
新米が美味しい季節であるこの時期に、お米から作られるお菓子「あられ・おせんべい」を食べてほしいという願いを込めて作られました。
毎年立冬(11月7日)には、あられとおせんべいを味わうのもいいですね。
鍋の日
立冬のころになると寒さが本格的になります。
そんな時期にもっと鍋を食べてほしいと鍋つゆを販売するヤマキが制定したのが「鍋の日」。
立冬のころから、夕食に鍋が登場する機会が増えるのではないでしょうか?
私の家ではキムチ鍋・味噌鍋・ちゃんこ鍋・トマト鍋・豆乳鍋・酸辣湯鍋・カレー鍋などをローテーションして味わいます。
中国の立冬の食べ物は?

立冬を含む二十四節気という暦上の取り決めは、古代の中国から伝来してきました。
ですから、立冬の「本家」といえるのが中国。
では、中国で立冬に食べるものは何かというと
- 北の地域:水餃子
- 南の地域:鶏肉や魚
といった食べ物を「特別なごちそう」として食べるそうです。
特に餃子を食べるのは有名で、それは餃子の発音が「交代」を意味する言葉と似ているため、そのような習慣が出来たと言われています。(立冬は「季節の交代」を意味するところから)
また、マイナス15度にもなる北京では冬の寒さで耳が落ちないように「耳の形に似た餃子」を食べるという風習もあるそうです。
面白い理由ですね!
主に北の地域で食べられる鶏肉や魚は「特別な食べ物」という印象はありません。
立冬のころになると北の地方では寒さが厳しくなるため、「栄養をつけて寒い冬を乗り越えよう」という意味を込めて食べられるそうです。
2025年の立冬はいつ?
今年2025年(令和7年)の立冬は何月何日になのかというと
この日付は毎年この日に決まっている!というわけではなくて、その年によって変動します。
だいたい11月7日か8日のどちらかに当たります。
11月22日は「小雪(しょうせつ)」になるので、その前日までの14日間が立冬の期間となります。
立冬は更に3つに分かれる
立冬は二十四節気のひとつですが、更に季節を細かく分けた七十二候という暦の分け方もあります。
それによると立冬は更に「初候・次候・末候」の3つに細かく分けられるんです。
初候/山茶始開(つばきはじめてひらく)

11月7日~11月11日ごろ。
つばきと書きますが、山茶花が鮮やかに咲き始める頃のことを言います。
次候/地始凍(ちはじめてこおる)
11月12日~11月16日ごろ。
大地に霜が降りて冷え込みが厳しくなる頃のこと。
末候/金盞香(きんせんかさく)
11月17日~11月21日ごろ。
金盞花ではなく水仙の花が咲き始める頃のこと。
立冬の意味と由来とは?
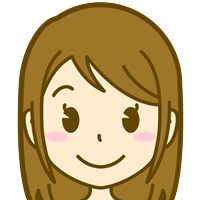
立冬って、どういう意味?
なんていうストレートな疑問をぶつけられても、余裕を持って答えられるように、しっかりと概要を頭に入れておきたいですね。
立冬とは、ざっくり説明すると
- 二十四節気のひとつ
- 冬の始まりを意味する日
- 木枯らしが吹き始める頃
- 立春・立夏・立秋と並ぶ季節(四季)の節目
- 立冬当日から小雪前日までが「立冬の期間」となる
- 立冬当日から立春前日までが暦上の「冬」とされる
- 太陽黄経が225度のとき
つまりカンタンにまとめると「立冬は冬がやってきた合図の日」ってことなんです。
二十四節気という一年の季節を24個に分けたうちのひとつで、暦上は立冬から冬の始まりになるわけですね。
立冬は、立春・立夏・立秋・立冬という4つの大きな区切りなので、季節の変わり目を知らせる役割として非常に大切に昔の人は捉えていたそうです。
立冬が「冬らしくない」理由とは?
立冬を過ぎると秋の穏やかな日差しから冬の弱々しい日差しに変わってきて、朝晩の気温がぐっと冷え込む時期ですよね。
しかし、昨今の地球温暖化の影響でまだ樹木の紅葉もまだまだこれからというのが普通。
ですので、冬が来たといってもピンとこないかもしれません。
コートを着るにはまだまだ早いくらいの暖かさが残っていますし・・・・・。
もともと立冬を含む二十四節気という暦の考え方は中国から来ています。
なので由来(ルーツ)は中国伝来なんですね。
ですから、その季節感は中国の気候(黄河の中流域)がベース。
中国と日本は近いようでいて、季節感には微妙なズレがあります。

立冬だけどまだそんなに寒くない
と感じるのは無理からぬことだと納得するしかありません・・・・。
また、立冬を含めた四立(立春・立夏・立秋)は、昼夜の長さを基準にして365日を分けて作られたもの。
よって実際の気候の「暑さ・寒さ」とは乖離があるのは当たり前なんですね。
まとめ
立冬の食べ物についてまとめてきました。
かぼちゃは間違いだというのは意外でしたね。
「これを用意すればいい」という行事食がなくて、拍子抜けした方もいるかもしれません。
そのかわりに「鍋」はいかがでしょうか?
気が早いお宅ではそろそろ鍋料理が食卓にのぼることがある時期。
私の家では毎年もっと遅くて12月になってからですが、今年は立冬を過ぎたら解禁しようかなって思います!