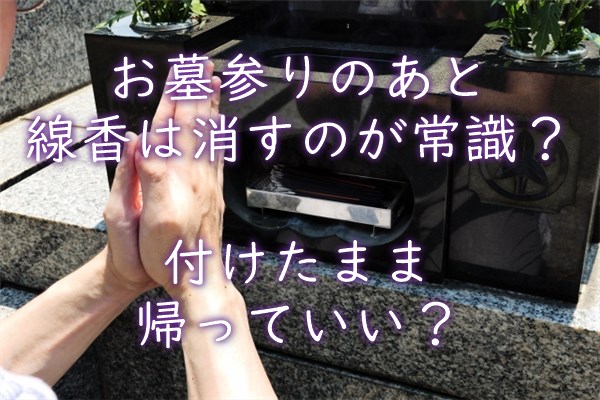
お墓参りをするときに欠かせない線香。
お墓を掃除して、花を供えて線香に火を付けて、ご先祖様にお祈りをして。
「さぁ、帰ろう」となったとき、線香の火はどうしていますか?
両親に連れられて行ってた頃は意識しませんでしたが、いざひとりで行くとなると、分からないことばかり……。
そこでお墓参りでの線香の火の始末についてや、行く時に必要な持ち物リストを両親に聞いて作成してみましたよ。
私みたいに不安に思ってる方に絶対に役立つはずです。
お墓参りをした後に線香の火は消す?

お墓参りが済んで帰るときに線香の火は消したほうがいいのか、それとも付けたままでもOKなのか、これについては仏教的なしきたりや常識はないようです。
ですから、あくまで墓地(霊園)の決まりに従うのが正しい判断となります。
墓地(霊園)の使用ルールに「線香の火は消してください」と記載されてあれば、消さなければいけませんし、そのような文言が無ければあえて消す必要はありません。
都心など狭いスペースにある墓地などは延焼など火事の危険性を恐れて、線香の火を消すのが決まりになっているケースが多いようですね。
もちろん、線香を焚く目的は亡くなった方への供養ですから、できれば線香の火が燃え尽きるまでお墓の前で待つのが理想でしょう。
しかし、一般的に使われている線香(長さ13~14cm)の場合、燃焼時間は約25分間。
忙しい現代人には25分もお墓の前でゆっくりと待つことはなかなか厳しいですよね?
ですから、ある程度、線香が燃えて煙が立ち上り、お墓参りに参加した人がすべてお祈りを済ませたら線香は消して帰りましょう。
線香の火を消す方法
さて、では帰るために線香の火を消すわけですが、どのように消したらいいか、これも迷ってしまいますよね?
一般的に線香の火は人の息を吹きかけて消すのは無作法とされ、手で仰ぐのが正しいとされています。
しかし、しっかり火がついて炎が立ち上っていない線香の火を消すには手で仰ぐだけではなかなか消えません。
そんなときはやや乱暴ですが、水を張ったバケツに火が付いた線香を入れて完全に鎮火させましょう。
大抵の墓地(霊園)ではお墓を洗うために自由に使える水道と、その水を運ぶためのバケツが用意されています。
お墓を洗うための水を少し残しておいて、それで消すようにすると良いと思います。
お線香の火の付け方
お墓参りでいちばん難易度が高い作業といえばお線香に火をつけることですよね。
特に風が強い日はライターを着火してもすぐ消えてしまって全くお線香が燃えてくれません……長くライターをつけていると持ち手のところが高温になってきて親指を火傷しそうになるし……。
そんなときは「風防ライター」という火が出る周りに風よけがついたライターを持って行くといいですよ。100円ショップでも売っています。
これなら多少風が吹いても火が消えませんし、指が熱くなることもありません。
これでもダメな時は、持参した新聞紙を丸めて火を付けて、それで線香に火を移すしかありませんね。あんまりマナーがいいことじゃないので積極的にオススメはしませんが。
※火事にならないようくれぐれもご注意ください。
お墓参りをするときの正しい手順
お墓参りをするときの正しい手順について、ざっとまとめておきますね。
- まず墓地の水場に用意されている桶に水をくみ柄杓と一緒に持っていく
- お墓の前に着いたら、お墓周辺の雑草を刈り取る
- 供えてあった仏花が枯れていたら取り除く
- 墓石をスポンジでこすって汚れを落とし、墓誌や外柵などを雑巾で拭く
- 「○○家之墓」や「享年を刻んだ文字」は凹んでいて汚れが溜まりやすいので歯ブラシでこする
- 水鉢や花立てに溜まった古い水を捨てて洗う
- 墓石全体に水をかけて洗い流す
- 仏花、故人の好物、線香を供える
- 墓前で手を合わせる(故人と縁の深い者から順番に)
このあと墓地のルールに従って線香を消して、借りたバケツや掃除用具などを所定の位置に戻して帰ります。
お墓に供えた食べ物は持ち帰る?
お供えした故人が好きだった食べ物などは、そのまま置いて帰るとカラスが食い散らかして汚くなります。
そういった後始末を墓地の管理者にまかせることになりますので、迷惑をかけないよう、お参りが済んだら片付けて持って帰ります。
タバコやお酒なども同様に時間が経てばゴミになりますので、持って帰ったほうが良いようです。
お墓参りの持ち物チェックリスト
お墓参りに行く際には線香の他にいろいろと持っていくべき持ち物がたくさんあります。
それをリストアップしましたので、お出かけの前にご確認ください。
- お線香
- 仏花
- お供え物(故人が好きだった食べ物や飲み物)
- ライター
- 掃除用具(たわし、スポンジ、歯ブラシ、雑巾など)
- 新聞紙(1枚で十分)
掃除用具については墓地(霊園)側で用意されていることも多いので、持っていく必要はないかもしれません。
墓地のホームページ等でご確認ください。
仏花を買うときの注意点
仏花というのはスーパーや霊園のそばで売られているお供え用の花束のことです。
墓石には花立が両サイドに2つあるように、2束でワンペアが常識です。
ですから仏花を買うときは必ず「2束セット」で買いましょう。
一般的に花束に使われるのは、菊・カーネーション・アイリス、ユリ、リンドウなどです。
でも、必ずこういう仏花として売られている花束でなければいけないわけではなく、故人が好きだった花をみつくろって持っていくのもありです。
花をばらで買うときは本数の合計は奇数にして、ひとつの花束としてまとめます(3本・5本・7本が一般的)
※しきたりとしてはバラのような刺のある花は供えてはいけないとされていますが、これも故人が好きであればぜんぜん構わないそうです。
お彼岸には「おはぎ」か「ぼたもち」を持っていこう
春と秋のお彼岸のお墓参りの際は、「ぼたもち」か「おはぎ」をお供えするのが常識ですので持っていきます。
この「おはぎ」と「ぼたもち」の違いですが、春のお彼岸に供えるのが「ぼたもち」で、秋のお彼岸に供えるのが「おはぎ」になります。
見た目も中身もまったく同じ食べ物がどうして名前が違うかというと、
春のお彼岸の頃に咲く花の牡丹から取って「牡丹餅(ぼたもち)」
秋のお彼岸の頃に咲く花の萩から取って「お萩(おはぎ)」
と呼ばれるようになったそうです。
これもカラスの格好の標的になりますので、お参りが済んだら速やかに片付けて帰りましょう。
まとめ
というわけで、お墓参りをしたあとの線香の火は消すのか消さないのか答えがハッキリしましたね。
墓地(霊園)のルールに従うというのが基本であり、もし火を消して線香を持ち帰るように決められていたら、バケツの水で完全に消化してゴミとして持ち帰りましょう。
ちなみに私の先祖代々の墓がある郊外の霊園では、特に線香の取り扱いについての細かな規則がありません。
そのため、お彼岸の頃に行くと他のお墓参りに来た人が残していった線香がまだ燃え残って煙を上げていることが多く、墓地全体が線香の匂いに包まれています。
私も家族揃ってお墓参りに行きますが、線香の火は付けたままですし、仏花やお供えした食べ物もそのまま置いて帰ります。
カラスの被害などがあるそうですが、墓地の管理者が頃合いを見計らって廃棄してくれているようです。

